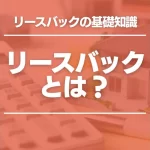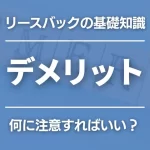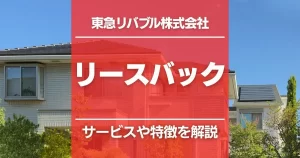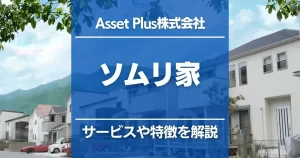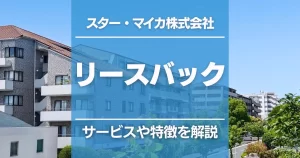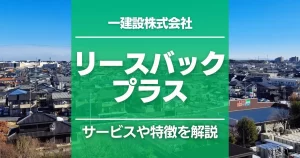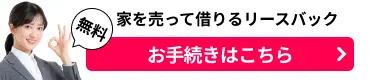不動産は遺産相続で、大きな課題となることがあります。金額が大きいものの、分割することが難しく、平等に分けられないためです。また、価値の低い不動産だと売却できなくて、相続後に放置されてしまうこともあります。
リースバックを利用すると、そういった課題を解決できるかもしれません。
相続対策にリースバックが利用できる理由やメリット、注意点などを解説します。終活でお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
相続対策にリースバックが活用できる理由
不動産は相続財産のなかでも、扱いの難しいもののひとつです。分割にくいほか、管理の負担などもあって、相続トラブルの原因になることがあります。そうした課題の解決策として注目されているのが「リースバック」です。リースバックの仕組みを活用すれば、不動産を現金化しながら住み続けられるため、相続対策として大きな効果を期待できます。リースバックの仕組みや相続対策になる理由をわかりやすく解説します。
リースバックの仕組みを解説
リースバックとは、自宅をリースバックの事業者(不動産会社など)に売却したあと、そのまま賃貸契約を結んで住み続けられる仕組みです。売却でまとまった資金を得ながらも、転居の必要がなく、生活環境を維持できることが特徴です。一般的なリースバックの契約の流れは次のとおりです。
- 自宅をリースバック会社に売却【所有権がリースバック会社へ移転】
- 自宅を売却した代金を受け取る
- リースバック会社と賃貸借契約を結ぶ【借主となる】
- 毎月家賃を支払いながら、引き続き住み続ける
リースバック会社や契約内容によって細かな部分は異なりますが、基本的な仕組みは以上のとおりです。
売却して相続財産に不動産を遺さない
不動産は「分けにくい資産」の代表格です。そのため、複数の相続人がいる場合、誰が不動産を相続するかで争いになるケースが少なくありません。被相続人があらかじめ自宅をリースバックで売却しておけば、不動産を相続財産として遺すことなく、分割しやすい現金という形で遺せます。これは、相続人同士での話し合いを円滑に進めるうえで大きなメリットになります。また、資産をめぐる不公平感が生まれにくくなるため、相続人同士のいさかいを未然に防げることも魅力です。残された家族が揉めることなく、円満に相続を進められるよう備えておくおとが、リースバックを活用する大きな意義といえるでしょう。
現金化されるので分割しやすい
リースバックで不動産を売却すれば、資産が現金化されます。現金は不動産と違って相続時に分けやすく、相続人同士の不公平感が生まれにくいのが特徴です。たとえば、不動産を遺してしまうと「住みたい人」「売って現金にしたい人」「公平に分けたい人」といった利害が衝突しがちです。しかし、現金であれば法定相続や遺言の内容にしたがってスムーズに分けられます。つまり、リースバックは相続財産を「分けられる形」に変える手段のひとつといえるでしょう。相続トラブルを回避し、家族の関係を良好に保つためにも、リースバックは有効な選択肢といえるでしょう。
空き家になるリスクを避けられる
近年、全国的に空き家問題が深刻化しており、総務省によると全国の空き家数は約849万戸、空き家率は13.6%にものぼります。空き家は建物の老朽化で破損したり、犯罪の拠点に利用されたりと多くの被害を周囲にもたらします。家族のために財産を遺そうと思ったのに、使わない不動産だと将来的な負担になることがあるのです。リースバックを活用すれば相続前に家を売却できるため、空き家になるリスクそのものを回避できます。さらに、売却後も住み続けられるため、「愛着のある家を手放さずに済む」という安心感も得られます。
参考:総務省「平成30年住宅・土地統計調査」
査定額・条件の比較は絶対!一括問い合わせで複数社にコンタクトできます!
リースバックで相続対策をするメリット
相続対策としてのリースバックには、不動産を現金化する以上の効果があります。たとえば、財産の分割をスムーズにし、なおかつ老後資金の確保や不動産維持の負担軽減、さらには高齢者施設への入居を見据えた住まいの選択肢など、多方面でメリットが得られます。リースバックによる相続対策の、具体的なメリットを見ていきましょう。
相続財産が分割しやすくなる
不動産は大きな資産である一方、遺産相続で分割しにくいという難点があります。特に預貯金や金融資産が少ない家庭では、不動産が財産の大半を占めるため、どう分けるかが相続トラブルの原因になってしまうのです。しかし、リースバックで不動産をあらかじめ売却、現金化しておくことで、遺産を相続人ごとに公平に分けられるようになります。被相続人が生前に分割しやすい形にすることで、相続人同士の対立や争いのリスクを軽減できるでしょう。
不動産の現金化で老後資金ができる
老後における最大の不安が「お金」です。生活費や医療費、介護費用など、先の見えない出費が続くなかで、預貯金だけで乗り切れるか不安を抱えている人も多いでしょう。リースバックを利用すれば、いま住んでいる自宅を売却してまとまった資金が得られます。そのうえ、自宅に引き続き住み続けられるため、高齢者の賃貸借契約の難しさもありません。老後の資金不足を補いつつ住宅を維持できるため、リースバックは心強いサービスといえるでしょう。
不動産を維持するコストがかからない
不動産を所有している限り、固定資産税や保険料、管理費、修繕費といったさまざまなコストが発生します。こういった維持コストは、年金生活の高齢者の負担としては軽くありません。しかし、リースバックで所有権を手放せば、これらの費用は基本的にかからなくなります。ただし、リースバックによる賃貸借契約では、一般的な賃貸借契約と異なり、軽微な修繕などを借主が負担するケースもあります。契約内容をよく確認し、想定される出費を事前に把握しておくことが大切です。
高齢者施設の空き待ちがしやすい
高齢者施設への入居を考えていても、希望する施設にすぐに入れるとは限りません。多くの施設では「空き待ち」の状態が続いており、それまでどこに住むかが問題になります。リースバックを利用すれば、施設入居のための資金を先に確保しつつ、入居までの期間はこれまでどおり自宅に住み続けることが可能です。転居のタイミングを自由に選べる点は、高齢期の生活設計において大きな安心材料となるでしょう。
相続対策でリースバックを利用するときの注意点
リースバックは相続対策に有効な方法ですが、メリットばかりに注目してしまうと、あとになってトラブルが発生することもあります。家族のすれ違いや、契約内容の誤解による後悔は避けたいところです。ここでは、リースバックを利用する前に押さえておきたい注意点を紹介します。
リースバックを利用する前に相談をする
相続人に無断でリースバックを進めると、思わぬトラブルにつながることがあります。たとえば「実家を売ってしまうなんて聞いていない」「将来自分が住むつもりだった」といった感情的な反発が起こることもあるでしょう。実家に対して強い愛着を持つ家族も多く、売却にさみしさを感じる人も少なくありません。
そういったことがあるため、リースバック会社のなかには、契約時に相続人の同意を必要とするところもあります。リースバックを検討する際は、相続人と話し合って理解と納得を得ることが大切です。
リースバックのデメリットを把握しておく
リースバックには魅力的な点が多い一方で、注意すべきデメリットもあります。契約を進める前に、次の点を理解しておきましょう。
- 買取価格は市場価格の60〜80%程度
- 家賃が周辺相場より高めになるケースが多い
- 定期借家契約となり、住める期間に制限があることが多い
- 再購入(買い戻し)ができない契約もある
不動産を現金化したいだけであれば、通常の仲介による売却のほうが高値で売れる可能性があります。目的に応じて、ほかの方法と比較・検討することが大切です。
必ずリースバックが利用できるとは限らない
リースバックはすべての物件に対応しているわけではありません。不動産会社は買い取った物件を将来的に再販売することを前提としているため、流通性が低いと判断された物件は、リースバックの対象外になることがあります。たとえば、極端に古い住宅や立地条件が悪い物件、再建築不可の土地などは、買い取りを断られることがあります。「申し込めば必ず利用できる」という前提ではなく、物件の評価や条件次第で断られることがあると理解しておきましょう。
契約内容や審査により利用条件が異なる
リースバックのサービス内容は、事業者によって大きく異なります。たとえば「住み続けられる年数」「家賃の設定方法」「買い戻しの可否」など、契約条件に幅があるため、1社の話だけを聞いて即決するのは避けるべきです。また、リースバックには事前審査があります。年齢、収入、希望物件の状況などによっては、希望する条件で契約できないこともあるため、複数社に相談して比較することが重要です。
リースバックはサービスの比較が欠かせない
リースバックは事業者ごとに家賃設定や契約年数、対応エリア、買い戻しの可否などが異なります。そのため、1社とだけ話を進めてしまうと、よりよい条件を見逃すことになりかねません。リースバックを検討しているなら、できるだけ多くの事業者の話を聞き、サービス内容や条件を比較することが大切です。「リースバック比較PRO」は、一度の入力で複数のリースバック会社にまとめて相談できる便利なサービスです。納得できる条件で契約を結ぶためにも、こうした比較サービスを上手に活用してください。
リースバックにはメリットがたくさん!一括問い合わせで各社の条件を比較しましょう!