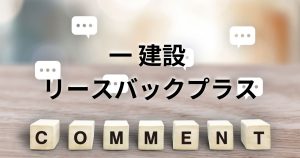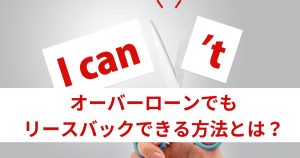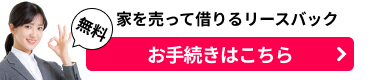リースバックを利用するときは、審査を受ける必要があります。住宅ローンを借りるときとは、審査の基準が異なりますので注意が必要です。またリースバックの利用には条件がありますので、依頼する前に確認しておきましょう。
まずはリースバックについて理解しましょう!
リースバックの利用には審査が必要
住宅ローンを利用するときに審査があったように、リースバックを利用するときにも審査が必要です。売却する自宅の不動産価値の審査はもちろん、それから賃貸借契約を結ぶため、賃貸の支払い能力についても審査を受けます。
リースバックで審査する2つのポイント
一般的なリースバックで行われる審査は、以下の2つです。
- 不動産価値
- 家賃の支払い能力
ただしリースバックは、金融機関からの融資とは性質が異なるため、不動産を担保にした住宅ローンのように収入や勤続年数などの信用情報を厳密に審査することはありません。
不動産価値
リースバックで売却する、自宅の不動産価値を審査します。重視するのは、住宅の資産価値(リセールバリュー)、売れやすさ(流動性)。です。将来的に売却することを視野に入れて、リースバック会社が独自に調査を行います。
また、物件の瑕疵や再建築の制限(法令上の制限)はないかなど、通常の査定とは異なる着眼点から物件の評価を行います。
家賃の支払い能力
不動産価値の評価ほど、個人の審査はそれほど重視されていないようです。そのため、高齢者や過去に金融機関の審査に落ちたことのある人でも、一定の条件を満たせばリースバックを利用できる可能性があります。
リースバックの利用に必要な条件
リースバックを利用するには、一定の利用条件を満たす必要があります。一般的には、以下2つがリースバックの利用条件です。
- 所有権者全員の同意がある
- オーバーローンではない
事前に調べられるものは、リースバックを申し込む前に調べておきましょう。
所有権者全員の同意がある
不動産の売却には、登記簿に記載されているすべての所有権者の同意(署名・捺印)が必要です。リースバックは、売買契約と賃貸借契約を同時に行うものなので、不動産売却と同じように、すべての所有権者の同意が必要です。
特に注意が必要なのが、相続で不動産を取得したケースです。こういったケースでは、相続人の数だけ所有権者が存在する可能性があります。また、複数の所有権者が存在していなくても、相続登記を怠って故人の名義のまま放置されているケースもあります。
相続以外では、所有権者が海外など遠隔地に住んでいたりする場合も考えられます。登記簿を確認して、契約にあたって問題がないか確認をしておくと良いでしょう。
オーバーローンではない
オーバーローンとは、不動産の売却額で住宅ローンの残り(残債)を完済できないことをいいます。
オーバーローンでリースバックを利用した場合、住宅ローンの残債と賃貸料の両方を支払うことになり、支払いが滞ってしまうおそれがあります。そのため、オーバーローンだとリースバックを利用できないことが多いです。
また、住宅ローンを組んでいる場合は、物件に抵当権が設定されています。所有権以外の抵当権・根抵当権・賃借権などは、登記簿の「乙区」欄に記載されています。所有権移転を行うには、これら記載されている権利をすべてて抹消しなければなりません。
抵当権は、必ずしも金融機関が債権者とは限りません。個人や企業が債権者となっているケースもあるので、債権者名義人が誰かを把握しておきましょう。
オーバーローンでもリースバックを利用するには、預貯金や親族からの借入などで差額を用意して抵当権を抹消し、オーバーローンを解消する必要があります。
住宅ローンの残高を調べるには
住宅ローンの残高は、借りている金融機関に出向く、または郵送などによる申請で確認することができます。重要な個人情報のため、電話で回答を得ることはできません。
利用条件は各社さまざま!まずは一括問い合わせで相談してみてください!
審査前に確認すべきポイント
審査の問題で借入が難しいという人でも比較的活用しやすいリースバックですが、利用する前には、いくつか確認しておきたいポイントもあります。
買戻しの条件は?
リースバックは、売却した物件を契約次第で将来買戻すことができることが特徴の一つです。
しかし、買戻しを前提にリースバックを利用したものの、予定通り買戻すことができないケースがあります。よくあるのは、買戻し金額を高額に設定されていたり費用や期限などを考慮していなかったりすることです。事前に確認しておきましょう。
また、買戻し権を行使する場合には、その資金を融資でまかなうのか、それとも自己資金でまかなうのかも考えておく必要があります。
リースバックの利用時点で住宅融資が確実に組める保証はありません。年収や年齢、健康状態などにより融資が組めない可能性も視野に入れ、検討しましょう。
サービス提供会社の経営状態は?
リースバックではサービス提供する会社の経営にも注意する必要があります。
通常のリースバック契約では、売買予約契約を締結し仮登記申請まで行うので、勝手に売却されることはありません。しかし、このような保全契約が行われていない場合には、リースバックを提供する会社が業績不振となれば「オーナーチェンジ物件」として売却される可能性もあります。
問題を抱えないためにも、リースバック利用時に確認しておきましょう。
賃貸借契約の種類は?
リースバックは賃貸借契約の種類によって、更新の可否が異なります。とくに、定期借家契約で且つ更新の特約を交わさない場合、更新をしたくても会社側都合によって賃貸借契約の更新ができない可能性があります。
条項をよく理解をしていない状態で、意図とは異なる契約書に署名捺印してしまうとトラブルに発展する可能性があります。「聞いていた話と違う」と抗弁しても双方の合意(私的自治の原則)が行われたと推察され、契約を覆すのは容易ではありません。
契約内容の理解に自信が持てない場合には、第三者の専門家に相談するなどの準備をしておく方が良いでしょう。
比較ナシで契約はしないで!一括問い合わせで条件を比較してみましょう!