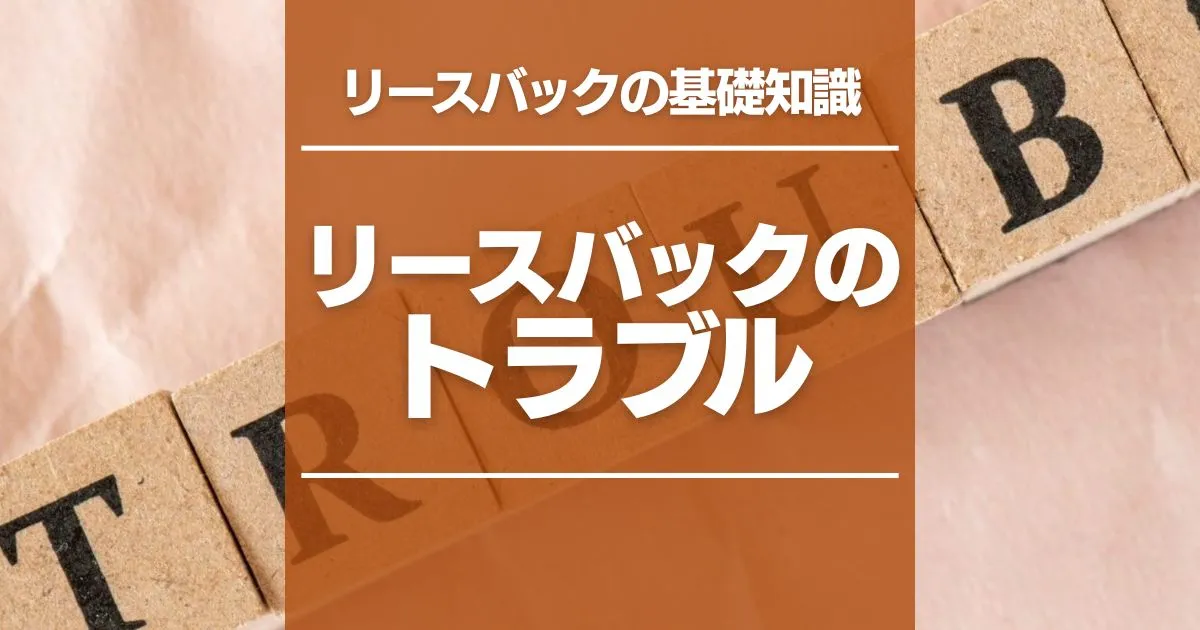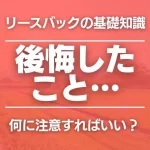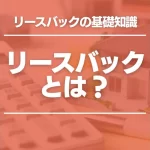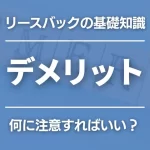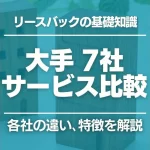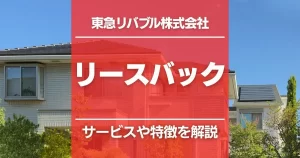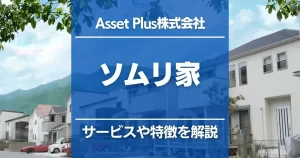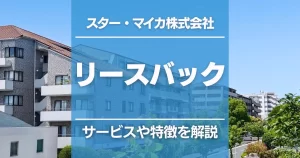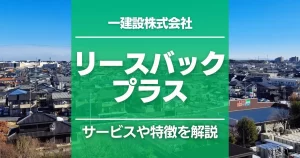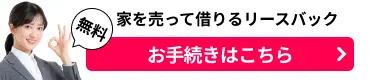不動産を活用した資金の調達方法として、リースバックが注目を集めています。しかし、トラブルの報告も多く、利用するときは慎重に検討することが求められます。リースバックはどうしてトラブルが多いのでしょうか。
この記事ではリースバックの利用を検討している人へ、リースバックでよくあるトラブル、トラブルが多い理由や対処法を紹介します。
目次
注意!リースバックのトラブルが急増中
自宅に住み続けながらまとまった資金を得られるリースバックは、一見すると魅力的なサービスです。しかしその裏で、「こんなはずじゃなかった」「契約内容に納得できない」といった声も急増しています。近年では、個人の問題を超えて、社会全体で注意喚起が行われるようになっています。
国民生活センターがリースバックに注意喚起
2025年5月、国民生活センターはリースバックに関する相談が急増しているとして、公式サイトで注意喚起を行いました。リースバックでは主に、次のようなトラブルが報告されています。
- 契約後に想定外の諸費用を請求された
- 家賃が高すぎて生活が苦しくなった
- 買い戻せると思っていたが断られた
これらのトラブルは、特に高齢者や単身世帯が内容をよく理解しないまま契約したことによる後悔の声が多く、社会的にも問題視されています。国民生活センターは、契約内容は必ず書面で確認し、不明点があれば家族や専門家に相談することを強く推奨しています。安易な契約は、生活の安定を脅かす危険性があると警鐘を鳴らしています。
参照:国民生活センター「リースバックに関する注意喚起」
国土交通省がリースバックのガイドブックを公開
リースバックをめぐるトラブルの増加を背景に、国土交通省は利用者保護の観点から、リースバックに関するガイドブック「住宅のリースバックに関するガイドブック」を策定・公開しています。このガイドブックでは、事業者によってサービス内容や契約条件に大きなばらつきがあること、そして契約形態が「売買契約」と「賃貸借契約」にまたがるため、仕組みが複雑で一般消費者には理解しにくいことが課題として指摘されています。
また対処法として、契約時に確認すべきポイントや、リスク回避のためのチェックリストが盛り込まれており、利用者が不利益をかぶらないように配慮されています。こうした公的機関の対応からも、リースバックは慎重に内容を理解し、安易に契約すべきでないサービスであることがうかがえます。
参照:国土交通省「「住宅のリースバックに関するガイドブック」 を公表しました」
リースバックでトラブルが多い理由
リースバックは、不動産売却と賃貸借を組み合わせた特殊な契約形態です。その仕組みの複雑さや、事業者ごとの対応の違いが原因となり、多くのトラブルを引き起こしています。ここでは、リースバックでトラブルが起こりやすい、主な理由を解説します。
リースバックのサービスがわかりにくい
リースバックは自宅を売却して資金を得ると同時に家賃を払って同じ家に住み続けるという、売買契約と賃貸契約が一体化した複合的な仕組みです。このふたつの契約が連動しているため、内容が複雑で一般の消費者には理解しづらいという特徴があります。
「売却したらすぐ退去しなければならないのでは?」「買い戻しは本当にできるのか?」といった疑問を持つ人も多く、十分な説明を受けずに契約を進めてしまうと、認識のズレからトラブルにつながることがあります。
実際に、「聞いていた話と違う」「そんな条件だったとは思わなかった」と後悔するケースも少なくありません。リースバックは仕組みをしっかり理解してから、判断すべきサービスといえるでしょう。
事業者によってサービスが異なる
リースバックは法律でサービス内容や契約条件が統一されているわけではなく、事業者によって内容に大きな違いがあります。たとえば、次のような項目は各社で対応が異なります。
- 家賃の設定方法(市場相場に連動しているかどうか)
- 契約期間(2年、5年、10年など)
- 契約更新の可否(定期借家か、普通借家か)
- 買い戻しの条件(価格、期限、手続き方法など)
- 修繕費の負担者(入居者かリースバック会社か)
こうした違いにより、他社との比較が難しく、「契約してから後悔した」という例も少なくありません。必ず複数社から見積もりを取り、条件を一覧表にして冷静に比較することが重要です。
契約した内容を正確に理解していなかった
リースバックをめぐるトラブルのなかでも多いのが、営業担当者の説明を信じて契約したが、実際の契約書には違う内容が書かれていたというケースです。高齢者や契約に慣れていない人の場合、細かな条文を確認せず、口頭での説明だけを鵜呑みにして署名してしまうことが少なくありません。
しかし、契約書は法的な効力を持つ正式な文書であり、たとえ口頭で「買い戻しは自由にできる」「家賃は変わらない」と言われていても、書面に明記されていなければその内容は保証されません。
あとから「そんな説明は受けていない」と主張してもとおらないことが多く、非常にリスクが高いのです。契約前には必ず、すみずみまで契約書を確認し、不明点があれば遠慮なく質問し、納得したうえで署名することが重要です。
周囲の人にあまり相談せずに契約した
リースバックは資金繰りや生活の事情といったデリケートな問題が関わるため、他人に相談しづらく、家族や友人、専門家に相談せずにひとりで契約を進めてしまう人も少なくありません。しかし、第三者の意見を聞かずに判断すると、不利な契約条件に気づかないまま契約してしまい、大きな後悔につながることがあります。
高齢者の場合、判断能力や契約経験に不安があると、事業者の言いなりになってしまうリスクもあります。大切な資産を扱う契約である以上、信頼できる第三者の助言を受け、慎重に進めることが重要です。
リースバック会社には悪質事業者が存在する
リースバック業界には、知識の乏しい利用者につけ込み、不利な条件で契約を結ばせようとする悪質な事業者も一部存在します。市場価格より極端に低い査定価格を提示したり、買い戻しが実質不可能な条件で契約させたり、契約後に「管理費」や「手数料」などの名目で高額な追加費用を請求するケースもあります。こうした悪質な事業者は、利用者が契約内容を十分に理解していないことを逆手に取り、強引に契約を進めることがあるため注意が必要です。
資産だけでなく法的紛争などに発展し余計な労力がかかるおそれがあります。リースバックを検討するときは、複数社を比較し、信頼できる不動産会社かどうかを慎重に見極めることが大切です。
よくあるリースバックのトラブル
実際にリースバックを利用した人のなかには、「こんなはずではなかった」と後悔している人も少なくありません。ここでは、よくあるトラブル事例を取り上げ、なぜそのような問題が起きるのかを具体的に紹介します。
- 家賃の負担が大きくて長く住み続けられない
- 買取価格が市場価格よりも安い
- 賃貸借契約の更新ができなかった
- 知らない間にオーナーが変わった
- 賃貸中の修繕が自己負担だった
- 再契約で家賃が大幅に上がった
- 相続人がリースバックに納得しない
- 価格が高すぎて買い戻しができない
- 高額な諸費用を請求された
- リースバックを利用できなかった
自分に起こりうる可能性があることとして、ぜひ参考にしてください。
家賃の負担が大きくて長く住み続けられない
リースバックでは、家賃が周辺の市場相場よりも割高に設定されることがあり、長期間住み続ける場合に経済的負担が大きくなる傾向があります。契約時には支払えると思っていても、年金収入の減少や医療費・生活費の増加など、将来的な支出の変化により家賃の支払いが困難になることもあります。
高齢者の場合、収入が固定されているため、当初の見込みどおりにいかず、結果として生活が破綻し、やむを得ず退去せざるを得なくなる事例も少なくありません。リースバックを利用する際は、数年先まで見据えた資金計画を立てることが重要です。
買取価格が市場価格よりも安い
リースバックの買取価格は、通常の不動産売買に比べて低めに設定されることが一般的です。多くの場合、市場価格の6〜8割程度にとどまることが多く、十分な相場の確認や比較、検討を行わないまま契約してしまうと、あとになって「もっと高く売れたのでは」と後悔するケースがあります。しかし、資金が急ぎで必要な場合は冷静な判断が難しく、不利な条件でも契約を進めてしまいがちです。
リースバックを検討する際は、複数の会社で査定を受け、仲介での売却とも比較したうえで、納得できる価格かどうかを慎重に判断することが大切です。
賃貸借契約の更新ができなかった
リースバックでは「定期借家契約」が多く採用されており、契約期間が終了すると自動更新がなく、原則として再契約も保証されていません。この仕組みを理解しないまま契約してしまうと、数年後に突然「契約満了なので退去してください」と通告され、慌てて住まいを探さなければならない状況に陥ることもあります。
高齢者や長期的に住み続ける前提で契約した人にとっては、大きな誤算となりかねません。契約時には「普通借家契約」との違いを明確に理解し、再契約の可否や今後の住まいの見通しについてもしっかり確認しておくことが、トラブル回避のポイントです。
知らない間にオーナーが変わった
リースバック会社は、買い取った物件を第三者に売却(いわゆるオーナーチェンジ)することがあります。そのため、利用者に事前の説明がないまま所有者が変わってしまい、新たなオーナーから家賃の値上げや退去を要求されるトラブルが起きることがあります。
契約時にこのリスクを知らされていなかったという相談も多く、「安心して住み続けられると思っていたのに」と戸惑う利用者も少なくありません。リースバックでは賃貸借契約を締結するため、第三者への譲渡に関する条項がどうなっているかを事前に確認しておくことが、将来の不安を避けるために重要です。
賃貸中の修繕が自己負担だった
一般的な賃貸契約では、給湯器やエアコンなどの設備故障はオーナーが修理を負担しますが、リースバックだと契約内容によっては借主(元所有者)が修繕費を負担することがあります。賃貸だから直してもらえると思い込んでいたために、突然の出費に驚く人も少なくありません。
高額な設備修繕が必要になった場合、生活費への影響も大きくなります。契約前には、修繕費の負担範囲について細かく確認し、どこまでが自己負担になるのかを明確に把握しておくことが重要です。曖昧な点がある場合は、事前に担当者から説明を受け、契約書に補足条項として明記してもらうと安心です。
再契約で家賃が大幅に上がった
リースバックで結ばれる賃貸借契約は、会社側のリスク管理により多くの場合「定期借家契約」です。そのため、期間満了後は自動更新されません。再契約を希望すると、リースバック会社から大幅な家賃の値上げを提示されるケースもあります。
当初の家賃を前提に生活設計をしていた人にとって、突然の値上げは家計を大きく圧迫します。収入が固定された高齢者にとっては深刻で、支払いが難しくなり退去せざるを得なくなることもあります。
こうした事態を避けるには、契約時に「再契約時の条件」や「家賃改定の可能性」について事前に確認し、必要であれば書面で明記しておくことが重要です。
相続人がリースバックに納得しない
両親がリースバックを利用していたことを知らなかった相続人が、実家がすでに第三者の所有になっていると知り、驚きや不満を抱くケースは少なくありません。「勝手に売られた」「買い戻せると思っていたのにできないのか」など、誤解から家族間のトラブルに発展することもあります。相続を見据えて実家を大切に考えていた子どもにとっては、突然の事実として受け入れがたいこともあるでしょう。
こうした問題を防ぐためにも、リースバックの契約を前に、推定相続人※に対して事情を丁寧に説明し、理解と同意を得ることが大切です。家族間で事前に共有しておくことが、あとの争いを回避する最善の手段です。
価格が高すぎて買い戻しができない
リースバックでは「将来的に買い戻しができる」と説明を受けていたので、買い戻しを希望すると、売却時よりもはるかに高額な価格を提示されるというケースがあります。買い戻しのトラブルは契約書に条件が具体的に明記されていない場合に起こりやすく、利用者が「誤解していた」「そんな話は聞いていない」と感じる原因になります。
リースバックの買い戻しはあくまでも任意条件であり、リースバック会社の都合で断られたり、高額な買い戻し額を提示されたりする可能性が高いのです。そのため、確実に買い戻しを希望している場合は、契約書に買い戻し価格や期限、方法などを明記しておきましょう。口約束では法的効力が弱く、後々のトラブルにつながるおそれがあります。
高額な諸費用を請求された
リースバックの契約では、「仲介手数料」「事務手数料」「管理費」などの名目で、高額な費用を請求されるトラブルが発生しています。契約時や更新時に思わぬ出費が発生し、当初の想定を大きく超えてしまうケースも少なくありません。
注意すべきなのは、契約書にこれらの費用が記載されていなかったり、記載があっても非常に曖昧な表現でわかりにくくなっていたりする場合です。こうした曖昧さを悪用するリースバック会社も存在するため、契約前に費用の内訳を明確に提示してもらい、不明点があれば必ず説明を受けましょう。納得できない項目があれば契約を見直す姿勢も必要です。
リースバックを利用できなかった
リースバックを申し込めば、誰でも利用できるわけではありません。査定の結果、希望する買取価格に届かなかったり、物件の状態や立地、築年数などの理由で対象外と判断されてしまったりするケースもあります。
地方の物件や流動性の低いエリアの住宅などは、リースバックの対象とならないことも珍しくありません。そのため、「必ず使えるもの」と思い込むのは危険です。事前に複数社へ相談・査定を依頼し、自分の物件が条件に合うのか、どの程度の価格で売却可能なのかを確認しておくことが大切です。事前準備を怠ると、計画に大きな狂いが生じることがあります。
そもそもリースバックとはどんなサービス?
リースバックのトラブルを正しく理解するためには、まずその仕組みをしっかり知っておくことが大切です。ここでは、リースバックの基本的な仕組みを、中立的な立場から解説します。
不動産買取+賃貸で資金を調達できる
リースバックは、国の制度ではなく、主に不動産会社や不動産買取業者などが提供している民間のサービスです。自宅を不動産会社に売却し、その売却代金を資金として得たうえで、同じ家に賃借人として住み続けられる仕組みです。また引っ越しの必要がないため、生活環境を変えずに済むという利点があります。
リースバックの利用目的はさまざまで、住宅ローンの返済資金や老後資金の確保、医療費・介護費用の捻出、さらには事業資金の調達など、状況に応じて柔軟に活用できます。通常の売却と異なり、住まいと資金を同時に確保できることから、特に高齢者世帯や資金繰りに悩む家庭にとって、現実的な選択肢のひとつとして注目されています。
家の売却後も家賃を払って住み続けられる
通常の不動産売却では、売却と同時に物件を明け渡さなければならず、引っ越しが避けられません。リースバックでは、売却後に賃貸契約を結ぶことで、同じ家に住み続けられます。所有権は不動産会社に移りますが、利用者は賃借人として家賃を払いながら生活を継続できるため、生活環境を維持したまま資金を得られるというメリットがあります。
子どもの学校や職場の都合、介護や近隣関係などの理由で引っ越しが難しい人にとっては、非常に有効な手段です。また、売却時の精神的負担も軽減されることから、シニア層を中心に利用が広がっています。
固定資産税などの維持費がかからなくなる
リースバックにより不動産の所有者が買主(不動産会社)に変わると、それまで所有者が支払っていた固定資産税や都市計画税の負担はなくなります。マンションの場合は、管理費や修繕積立金も所有者の義務となるため、これらの支出も不要となるケースが一般的です。
結果として、日常の生活費に占める「住まいの維持コスト」が大幅に削減され、家計の改善につながることもあります。年金生活者や収入に限りがある家庭にとっては、毎年発生する支出を抑えられる点が大きなメリットです。
このように、リースバックは維持費の軽減によって、老後の資金計画を見直す手段としても有効です。
トラブルなく利用するにはリースバック会社を比較できる“リースバック比較PRO”をご利用ください!
リースバックのデメリットに注意が必要
リースバックには魅力的な面も多くありますが、安易に契約してしまうと思わぬ落とし穴にはまってしまうこともあります。ここでは、利用前に必ず理解しておきたい、リースバックの主なデメリットを解説します。
- 市場価格より買取価格が安くなる
- 周辺の相場よりも家賃が高い
- 賃貸借契約によっては更新ができない
それでは、ひとつずつ見ていきましょう。
市場価格より買取価格が安くなる
リースバックでは、売却価格が通常の不動産仲介よりも低く設定されるのが一般的です。多くの場合、相場の6〜8割程度の価格での買取となるため、「もっと高く売れたのでは」と後悔するケースもあります。
仲介売却では時間や手間がかかる一方、リースバックは迅速に現金化できるという利点がありますが、そのスピードと引き換えに価格が下がることを理解しておく必要があります。資産価値の高い不動産を手放す場合は、事前に通常の売却価格と比較しておくことが大切です。査定内容の根拠をリースバック会社に確認し、納得できる価格かを慎重に見極めましょう。
周辺の相場よりも家賃が高い
リースバックでは、将来の家賃収入を見込んで買い取る価格を決定します。そのため、リースバック会社は高めの家賃を設定する傾向があります。高利回りを重視するリースバック会社の場合、周辺の相場よりも1〜2割高い家賃になることもあり、長期的に見ると支出が増えてしまうケースも少なくありません。
たとえば、10年以上住み続けた場合、家賃の総額が売却価格を上回ることもあります。契約時には「いま払えるか」だけでなく、「今後も無理なく支払い続けられるか」という視点も必要です。将来的な収支シミュレーションを立てて、家計への負担を冷静に判断することが重要です。
賃貸借契約によっては更新ができない
多くのリースバックでは「定期借家契約」が採用されています。これは契約期間が満了すると自動更新されない契約で、再契約の保証もありません。そのため、一定期間が過ぎたあと「再契約不可」となり、退去を求められることがあります。契約時に「住み続けられる」と思い込んでいた人にとっては、突然の退去通告が大きな負担になるでしょう。
長く住み続けたい意思がある場合は、契約前に更新可・再契約の有無などの条件を必ず確認し、書面で残しておくことが重要です。また、定期借家契約と普通借家契約の違いも理解しておく必要があります。
トラブルを回避するために必要なこと
リースバックは非常に便利な仕組みですが、正しく理解せずに契約すると後悔するリスクがあります。ここでは、トラブルを未然に防ぎ、安心してリースバックを利用するために押さえておきたいポイントを解説します。
そもそもリースバックが必要なのかをよく検討する
リースバックは便利な仕組みですが、ほかにも選択肢があることを知ったうえで、慎重に判断することが重要です。リースバックの代わりとなるサービスを次の表で比較しました。
| 方法 | 特徴・仕組み | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| リースバック | 自宅を売却し、同時に賃貸契約を結んで住み続ける |
|
|
| リバースモーゲージ | 自宅を担保に、金融機関からお金を借りる(死後に物件売却で返済) |
|
|
| 仲介による売却 | 不動産会社に買主を探してもらい、市場価格で売却する |
|
|
| 不動産担保ローン | 自宅を担保にして金融機関から融資を受ける |
|
|
どの方法にも一長一短があるため、目的や生活状況に応じて慎重に比較・検討することが大切です。家族や専門家に相談することで、より客観的な判断ができるようになるでしょう。
それぞれの仕組みやメリット、デメリットを比較し、自分の経済状況や将来設計に最適な手段かどうかを冷静に見極めることが重要です。
契約書の内容をよく確認する
リースバックでトラブルが起こる原因のひとつは、「契約書の内容を正確に理解していなかった」ことです。営業担当者の説明が丁寧でも、最終的に効力を持つのは契約書の記載内容です。次の項目は、契約前にしっかり確認しておきましょう。
- 家賃の金額と支払い条件
- 契約期間と終了後の対応(再契約の可否)
- 買い戻しの条件(価格、期限など)
- 修繕費の負担者と範囲
契約書に不明な言葉や曖昧な表現がある場合はそのままにせず、納得するまで質問しましょう。可能であれば、司法書士や不動産の専門家に内容を確認してもらうとより安心です。
リースバック会社のサービス内容を比較する
リースバックは、事業者ごとに契約条件や対応方針が大きく異なります。特に次の項目は会社ごとに内容が違うため注意が必要です。
- 買取価格の設定基準
- 家賃の決め方(相場連動か固定か)
- 契約更新の可否(再契約の有無)
- 買い戻しの条件(価格、期限、方法など)
1社だけで即決せず、必ず複数社から見積もりを取りましょう。条件を表にまとめて家族と一緒に検討するのもおすすめです。価格や契約内容に加え、担当者の対応や信頼性といった「人の印象」も重要な判断基準になります。焦らず冷静に、信頼できる事業者かどうかを見極めることが、後悔しない契約につながります。
希望があれば相談して契約書に記載する
「将来的に買い戻したい」「子どもと住み続けたい」などの希望がある場合は、必ず契約書にその旨を明記してもらいましょう。口約束はあとから言った、言わないのトラブルになるリスクがあり、法的な効力もほぼありません。
買い戻し条件や家賃の据え置き、修繕の負担などについて希望がある場合は、事前に話し合い、可能であれば「特約」として書面に明記しておくと安心です。遠慮せずに希望を伝え、それが実現できるかどうかを交渉する姿勢が、リースバックで後悔を防ぐ鍵になります。
契約前に相続人にリースバックの利用を相談する
両親がリースバックを利用したことを知らなかった相続人が、あとから知って驚いたり、不満を抱いたりするケースは少なくありません。「実家を勝手に売られた」と感じられてしまうと、家族間のトラブルに発展するおそれもあります。
そうした事態を避けるためには、契約前に推定相続人(子どもや配偶者など)にリースバックを検討していることを伝え、理由や背景をしっかり説明しましょう。理解と納得を得たうえで契約に進むことで、将来的な不和を未然に防げます。
安心してリースバックを利用するなら一括査定サイトがおすすめ
リースバックで後悔しないためには、最初の「リースバック会社選び」が重要です。悪質なリースバック会社にあたってしまうと、金銭面でも精神面でも大きな負担を抱えることになります。信頼できるリースバック会社と出会うためには、「一括査定サイト」の利用をおすすめします。
複数のリースバック会社にまとめて査定を依頼できる
リースバックの一括査定サイト「リースバック比較Pro」を利用すれば、複数のリースバック会社に対して、同時に査定を依頼できます。1社ごとに問い合わせをする手間が省け、複数の不動産会社の提示条件を比較することで、自分にとってもっとも有利な選択肢が見つけられるのです。
また、リースバック比較Proで複数の不動産会社に相見積もりを依頼することで、リースバック会社も不当な条件を提示しにくくなるというメリットがあります。結果として、悪質なリースバック会社を自然に排除し、信頼できるリースバック会社と出会える確率が高まります。査定は無料なので、「前向きに話を聞いてみたい」という段階でも気軽に利用できます。
トラブルなく利用するにはリースバック会社を比較できる“リースバック比較PRO”をご利用ください!