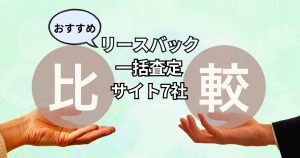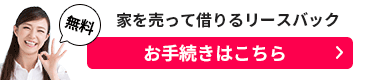リースバックは、不動産や金融の専門家でもない限り、多くの方にとって馴染みのない取引です。そのため、リースバックを利用した後で、それを知らなかったことが原因でトラブルになることもあります。
「事前に知っていればこんなことには…」と後悔しないためにも、トラブルを避けるために役立つ基本的なことを確認しましょう。
トラブルなく利用するにはリースバック会社を比較できる“リースバック比較PRO”をご利用ください!
リースバックによるトラブルが問題に!
リースバックとは自宅の売却と賃貸借契約を同時に交わすことで、そのまま住み続けられる仕組みのことです。売却によって資金調達を行いつつ、賃貸借契約で引っ越さずにそのまま自宅に住めるのがメリットです。
しかし、リースバックではトラブルが少なくありません。
2022年6月24日、国土交通省は「住宅のリースバックに関するガイドブック」 を公表しました。
リースバックによる不動産取引の増加にともない、サービス内容を十分に理解せずに契約したり、悪質なリースバック会社が強引に契約を迫ったりといったトラブルが発生しています。こういった状況を受けて国土交通省は、有識者や業界団体で構成される「消費者向けリースバックガイドブック策定に係る検討会」による検討を進めて、ガイドブックをとりまとめました。
参考:国土交通省「「住宅のリースバックに関するガイドブック」を公表しました」
リースバックはまだ新しいサービスで、内容がよく理解されていなかったり、会社によってサービス内容に違いがあったりするため、トラブルが起こりやすいのです。リースバックの利用を検討している人は、さまざまなトラブル事例を参考に、比較・検討を重ねたうえで契約するリースバック会社を選びましょう。
リースバックでよくある6つのトラブル
リースバックではさまざまなトラブルが起こりますが、契約内容の見落としが原因になっていることが少なくありません。どのようなトラブルが発生しているのか紹介します。
- 再契約で家賃が高くなった
- 新しいオーナーに退去を迫られた
- 賃貸借契約の更新を断られた
- 家賃が高すぎる
- 所有権が移転しているため相続できなかった
- 買い戻しの価格が売却したときより著しく高い
再契約で家賃が高くなった
リースバックは売却した自宅に、家賃を払って住み続けるサービスです。ところが賃貸借契約を再契約するときに、家賃が大幅に高くなって住み続けられなくなるトラブルが起こっています。
トラブルが起こる原因
リースバックでは主に「定期借家契約」が利用されています。定期借家契約は賃貸できる期間が決まっており、契約期間より長く住むには再契約が必要です。
再契約で家賃などの条件をあらためて決めるため、前の契約より家賃が高くなることがあります。再契約の条件に同意できないのであれば、退去しなくてはなりません。
トラブルを防ぐには
長く住み続ける予定であれば定期借家契約ではなく、「普通借家契約」を交わしましょう。
定期借家契約と普通借家契約の違い
- 定期借家契約
-
- 賃貸できる期間が決まっている
- 契約期間より長く住むには再契約が必要
- 普通借家契約
-
- 契約を更新できる
- 契約の更新は借主の意志で決まる
普通借家契約は賃貸住宅に住むときに利用される、一般的な賃貸借契約です。契約は一定期間ごとに更新され、家賃などの条件が変わることはまれです。
長く住み続けるのであれば、普通借家契約を利用できるリースバック会社を選びましょう。
新しいオーナーに退去を迫られた
自宅をリースバック会社から購入した新しいオーナーが、退去を要求してトラブルになることがあります。
トラブルの原因
リースバックでは自宅の所有権は、リースバック会社が所有しています。そのため、リースバック会社はもとの所有者に確認することなく、第三者へ自宅を売却できます。
新しいオーナーが転売して早く利益を出したいと考えている場合、退去を求められることがあります。
トラブルを防ぐには
賃貸借契約で決めた期間中は、新しいオーナーがどんなに要求しても退去する必要はありません。家賃を滞納しているなど借主に契約への違反行為がなけば、貸主である新しいオーナーが要求しても対応は不要です。
ただし、定期借家契約を利用している場合、期間満了後の再契約を拒否されることがあります。再契約には双方にも同意が必要なため、再契約できなければ退去することになります。
退去せずに長く住み続けたいのであれば、賃貸借契約に普通借家契約を選べるリースバック会社を選びましょう。また、倒産などで第三者に所有権がわたらないよう、大手のリースバック会社を選ぶのもポイントです。
| サービス名 | 提供会社 |
|---|---|
| ハウス・リースバック | 株式会社And Doホールディングス |
| セゾンのリースバック | 株式会社セゾンファンデックス |
| あなぶきのリースバック | 穴吹興産株式会社 |
| 東急リバブルのリースバック | 東急リバブル株式会社 |
| リースバックプラス+ | 一建設株式会社 |
定期借家契約でも、借主の希望で再契約ができるリースバック会社もあります。
| サービス名 | 提供会社 |
|---|---|
| 売っても住めるんだワン!! | 株式会社センチュリー21・ジャパン |
| 安住売却(あんばい) | 株式会社インテリックス |
リースバック会社の比較は“リースバック比較PRO”が便利です!ご自宅に対応できる会社をご紹介します。
賃貸借契約の更新を断られた
一般的な賃貸住宅であれば、賃貸借契約の更新を断られることはありません。しかし、リースバックでは、賃貸借契約を断られてトラブルになることがあります。
トラブルの原因
再契約が必要な定期借家契約だとリースバック会社の同意が得られないと、そのまま住み続けられません。リースバック会社が再契約を拒否すると、契約満了をもって退去が必要になります。賃貸借契約の違いをよく理解しておきましょう。
| 定期賃貸借契約 | 普通賃貸借契約 | |
|---|---|---|
| 賃貸借の期間 | 2~3年が一般的。それ以上は再契約が必要。更新はできない | 2年が一般的。契約更新でさらに住み続けられる |
| 契約更新・再契約 | 再契約には貸主の合意が必要 | 借主の意思で更新が可能 |
| 賃料の変更 | 可能 | 貸主に正当な理由があれば可能 |
トラブルを防ぐには
長く住み続けるのであれば、普通借家契約を利用できるリースバック会社を利用しましょう。ただし、賃貸住宅を借りるのと同じように、家賃を滞納するなどの素行不良があると契約期間中でも契約解除を申し立てられるおそれがあります。
あくまでも、自宅の所有者はリースバック会社ということを忘れないよう注意してください。
家賃が高すぎる
周辺の相場よりリースバックの家賃が高く、トラブルが起こることがあります。あまりにも家賃が高いと、10年ほどで売却価格と同じだけの金額になってしまうのです。
トラブルの原因
リースバックの家賃は周辺の相場ではなく、買い取った自宅で利益を出すために期待利回りを設定し、それをもとに家賃を算出します。
年間の家賃が売却価格の10%だとすると、10年間住み続けると売却代金と家賃でプラスマイナスゼロになってしまうわけです。
トラブルを防ぐには
対策としては、次の方法があります。
- 売却価格を安くする
- 定期借家契約を選ぶ
売却価格が安くなると、それだけ家賃も安くなります。長く住み続けることが目的であれば、売却価格を安くするのもひとつの方法です。
また、普通借家契約と比べると、定期借家契約のほうが期待利回りが低くなります。つまり、それだけ家賃を抑えられるのです。ただし、定期借家契約は住める期間が決まっているため、長期の賃貸には向いていません。
所有権が移転しているため相続できなかった
自宅を相続するつもりだったのに、リースバックで売却されてしまって相続人とトラブルになることがあります。
トラブルの原因
リースバックは相続財産の整理や介護施設への入所資金などを目的に、高齢者が利用することが多いサービスです。ところが、リースバックはそのまま自宅に住み続けられるため、売却したことを相続人が知らないままになってしまうことがあります。
トラブルを防ぐには
リースバックを利用する人が高齢の場合、必ず相続人に相談しましょう。相続人がリースバックを正しく理解していないと、「騙されたのでは」と不安に思うおそれがあります。自宅を売却することを相続人に話し、理解してもらったうえでリースバックを利用しましょう。
リースバック会社によっては、相続人すべての許諾を得ることが条件になっている会社があります。面倒に思うかもしれませんが、安心して利用できるでしょう。
買い戻しの価格が売却したときより著しく高い
リースバックは契約したときに、「買い戻し」の特約をつけられます。買い戻しとは、リースバックとして利用したあと、代金を払って所有権を取り戻す仕組みです。ところが、買い戻しの価格が、売却したときよりも高い金額を提示されてトラブルになります。
トラブルの原因
基本的にリースバックの買い戻し価格は、自宅を売却したときより高くなることが一般的です。買い戻し価格は、売却価格の1.1~1.3倍が目安です。
利用者が買い戻し価格が高くなることを認識していなかった、悪質なリースバック会社が約束した買い戻し価格を守らないなどが原因として考えられます。
トラブルを防ぐには
まず、買い戻し価格が売却価格より高額になることを、利用する人が認識しておくことが大切です。そして、リースバック会社に対して、買い戻し価格がどれくらいになるかを利用前に確認しましょう。
また、リースバック会社によっては、買い戻し価格を引き下げるサービスを提供しています。一建設のリースバックプラス+では、住む期間が長くなるほど買い戻しの価格が下がるプランを用意しています。
リースバック会社によって提供するサービスに違いがあるため、利用するときは必ず複数社に相談することが大切です。
リースバック会社によってサービス内容が違います。一括問い合わせで複数社に相談してください
リースバックのトラブル対策 3つのポイント
リースバックのトラブル事例をふまえて、回避するための3つのポイントを紹介していきます。
リースバックの契約書をよく読み、勘違いをなくす
トラブル発生原因の多くは、借主が契約内容を誤解していることにあります。
不動産売買の契約書は、専門的な用語が多く、つい読み飛ばしてしまいがちです。しかし、重要なことが記載されているからこそ難しいと考えることができます。認識との齟齬がないよう、一度はすべてに目を通しておくべきでしょう。
契約書で不明な点があれば、リースバック会社に直接確認しても良いでしょう。その場合は、口頭の説明が証拠にならないことに要注意です。トラブルが発生したタイミングで説明不備を指摘しても話が通ることはほとんどないため、メールなどで文書化してもらうことが重要です。
家族や遺産相続人などには存命中に相談しておく
もう一つ重要なことは、家族や重要な遺産相続人には事前に相談し、極力、了承を得ておくことです。
最終的に決める権利は住宅所有者にあるとはいえ、遺産総額に大きな誤認があるとトラブルの元になることは言うまでもありません。特に同居する家族が遺族となった時には、重大な影響を受ける可能性もあります。したがって、リースバック契約を行ったことは存命中に伝えておくことをおすすめします。
リースバック後、退去するか、別の住まいに移るかを考えておく
リースバックでは、契約の更新や再契約によって自宅を賃貸し続けることができます。しかし、ずっと住み続けるつもりなのか、一定期間が立てば引っ越したり高齢者向けの施設に入ったりするつもりなのか、ある程度決めておくことが大切です。
また、契約するリースバック会社によってはそもそも、一定期間で退去しなくてはならないこともあります。事前に条件を比較し、見極めておくことも重要でしょう。
住み続ける契約も可能です!一括問い合わせで会社の条件を比較しましょう!
複数のリースバック会社に問い合わせて比較する
トラブルを防ぐため、リースバックの契約をするときは、複数のリースバック会社に問い合わせてください。リースバックは会社によって提供するサービスが異なるため、各リースバック会社と相談して比較することがトラブル予防につながります。
複数のリースバック会社へ問い合わせるときは「リースバック比較PRO」が便利です。自宅の情報や連絡先を一度入力するだけで、複数のリースバック会社に問い合わせられます。
登録しているのは審査を通過したリースバック会社だけなので、悪質なリースバック会社に契約を迫られる心配もありません。
リースバックを検討している方は、ぜひリースバック比較PROからお申し込みください。
トラブルの防止は条件の比較が大事!一括問い合わせで各社に相談してみましょう!
リースバック
リースバックとは?【不動産のリースバックを徹底解説】
リースバックは詐欺なのか。「闇がある」と言われる理由を解説
リースバックは怪しい?罠がある?その答えとは
リースバックの相談先3選とトラブル時のサポート先3選を詳しく解説
リースバックのよくある後悔9つと対策!選択を間違えないためには?
リースバックは罠?それとも救世主?公平に「善」か「悪」か、徹底検証